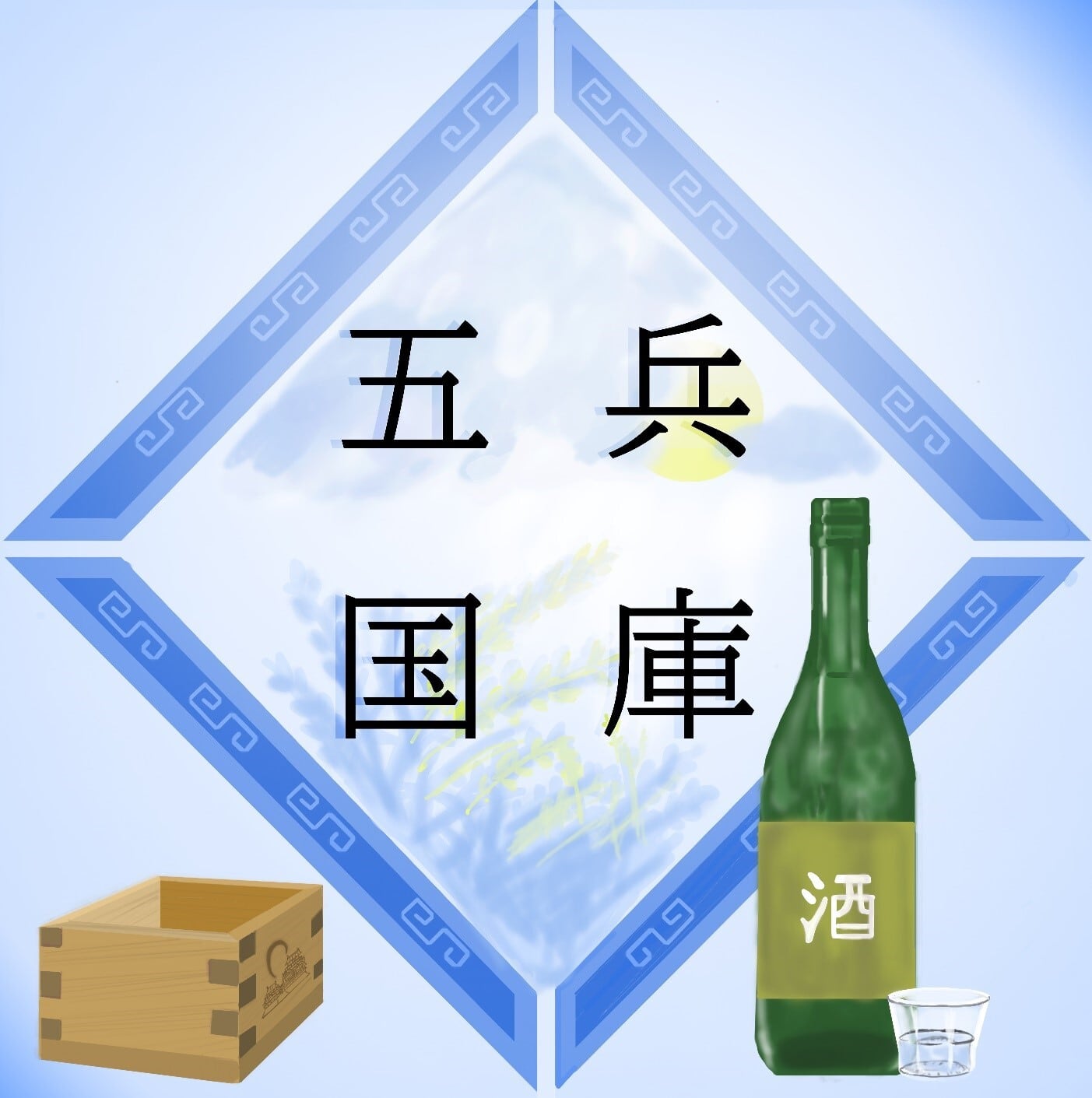2022/04/18 05:57

日本酒の歴史を支えてきた三大杜氏集団
江戸時代に生まれた杜氏制度ですが、やがて杜氏集団が形成されるようになります。
この目的は、杜氏集団内で品評会や講習会を行い、情報交換をしながら切磋琢磨し、造りの技術をさらに高めていくことにありました。
杜氏集団は北は青森から南は長崎まで全国にあり、各集団によって造りの方針が異なります。「酒屋万流」と言われる、それぞれの日本酒の多種多様な個性はここから生まれてくるといっても過言ではありません。
各地に存在する杜氏集団の中でも、とりわけ影響力の強い3つが「三大杜氏集団」と呼ばれています。
その三大杜氏が、南部杜氏(岩手県発祥)、越後杜氏(新潟県発祥)、丹波杜氏(兵庫県発祥)です。
丹波杜氏
丹波杜氏は、現在でも日本有数の日本酒生産地として知られる、神戸市灘区の周辺に端を発する杜氏集団です。具体的には、丹波篠山と呼ばれる、旧多紀郡が発祥と言われています。
伊丹・池田で酒造りを始め、摂津国灘五郷でその技術を開花させ、灘の地を一大生産地におしあげました。
今後、日本酒を楽しむ際には、「どんな酒米で、どれくらいの精米歩合で造られたのか」「どんな造り方で、どんな味わいなのか」という観点だけでなく、「どんな杜氏が造ったのか」という点に着目してもおもしろいかもしれませんね。
ホームページSAKETIMEより抜粋